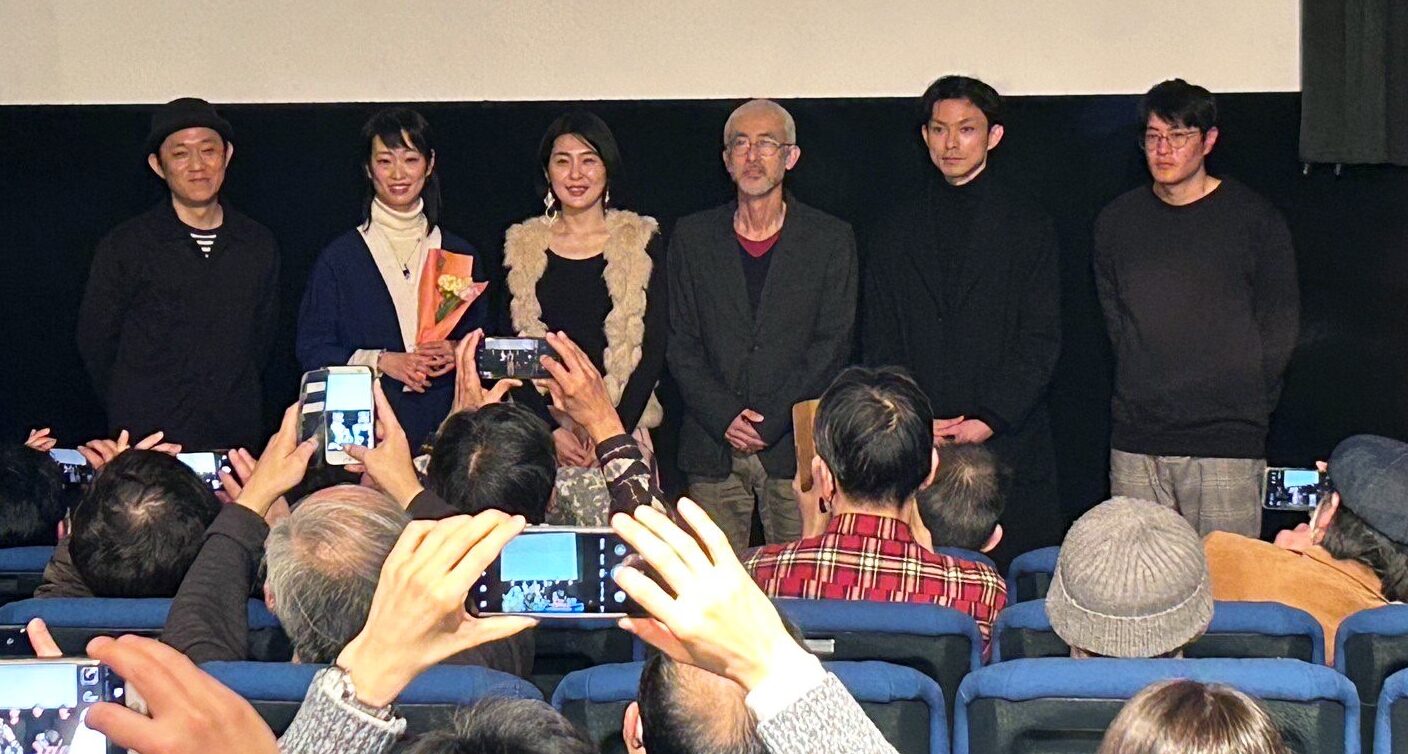「Vol.6」
一人目に出会う人物との会話までの脚本を書いた私は、「結局、やってみないと分からないんだな」と思った。

会話が始まるまでは「場」と「大まかな行動」しか書かれていないし、主人公が高橋恭子演じる人物と会った後も、そこに台詞が
加わっただけだ。
テストで指針は得ていたが、結局何が撮れるか分かるわけではなかったのだから、「やってみないと何も分からない」。
私は続きを書こうとはせず、そこまでを撮影してみることにした。
続きをどうすべきかは、その結果次第で考えればいい。
乱暴なやり方ではあるが、他のやり方は思いつかなかったし、結末もそうして積み重ねたもの次第で生まれてくるのだろう。という風に考え始めていた。
この辺りでもう、「一定量の脚本を書き、その部分を撮影し、続きを書いてはまた撮影する」ということを繰り返す、この映画の撮影スタイルが決まっていたのだと思う。
まずは序盤、主人公一人の部分の撮影から始めた。
自分でカメラを回す事は決まっていたし、特に面倒な準備物もないので、撮影現場は石川理咲子と私の二人だけだった。
今更の説明ではあるが、この映画を撮り始めるにあたってはまともな予算などありはしなかった。
想定していた予算も30万円程度の、私の自己資金による自主映画である。
出演者への少ないギャラと、食事代やレンタカー代程度。
自分で撮影も照明もある程度組めると考えていたし(そもそも、照明なんていらない。光はどこにでもあるし、暗いところでは映らないのが当たり前だ。と思っていた)、アフレコを前提としているので、録音はアフレコのガイドになれば良いというレベル。
基本的にはスタッフは自分一人で。
何かの事情で人手が必要な場合は、無料でも手伝いに来てくれる昔からの仲間がいた。
出演者には申し訳ない点も多かったが、かねてから「できる限り小さな規模で映画を撮りたい」とも考えていた私は、この映画ならやれると感じ、本当の最少人数で撮影をしていくことにした。