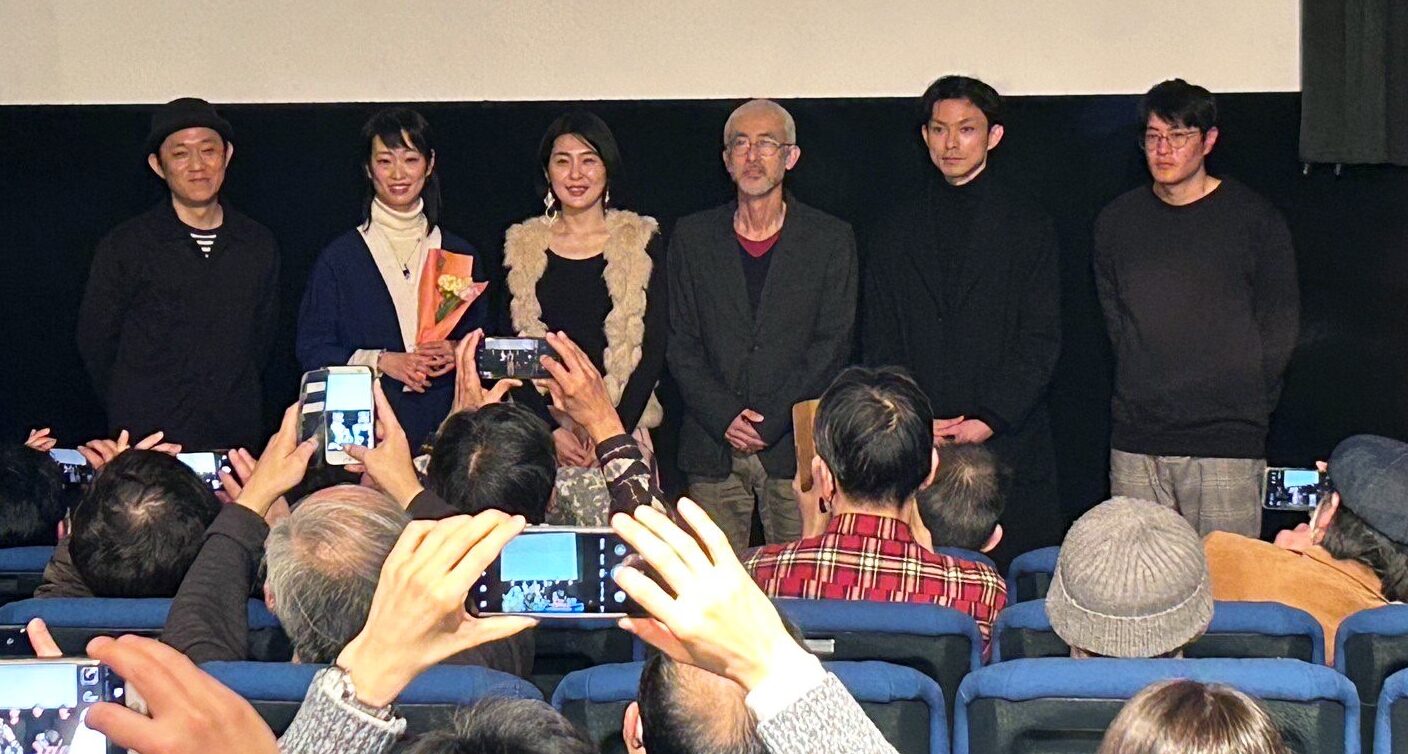「Vol.2」
とにかく「現実に近い=リアル」という考え方は既に持っていなかった。

勿論それを映画に持ち込む事には一定の価値があるが、「映画には別の方法でリアリティを構築することができる」そして「そこにこそ映画の、映画にしかない大きな価値があるはずだ」と考えていた。
これまでの映画制作の中で、技術的な一つの方法は見つけていた。
アフレコだ。
師である帯谷有理氏により、恐らく私は音について考える機会を他の映画制作者たちより多く与えられていた。
同時録音にもアフレコにも何度か取り組み、前作では「アフレコの音による“違和感”と“それに慣れること”を繰り返すことで、リアリズムに対する一般の価値観を揺さぶる」事に挑戦し、成功とは言えずとも一定の手応えは得ていたのだ。
演技において考えていた事は、画面内での身体的な動きにより、画面構築と連動して一般的な映画に無い何かを表現すること。
言葉というツールが、所謂リアルな芝居でなされる次元から別の次元に向かえるようにすること。
感情と身体と画面構築が表現できる物を共に模索していける人物。
そう思った時に閃いたのが、石川理咲子だ。思いついた途端「この映画の主人公は役者である必要なんて無い」という事を理解した。
どう伝えたかは憶えていない。
確か電話でそれまで考えていた事を話し、一緒に何か映画を作ることははできないか、と持ちかけただけだ。
色々と考えていたが、私にも何をすればどうなるか?などということは分からない。
「何ができるか分からない」共通認識はそれだけだったと思う。